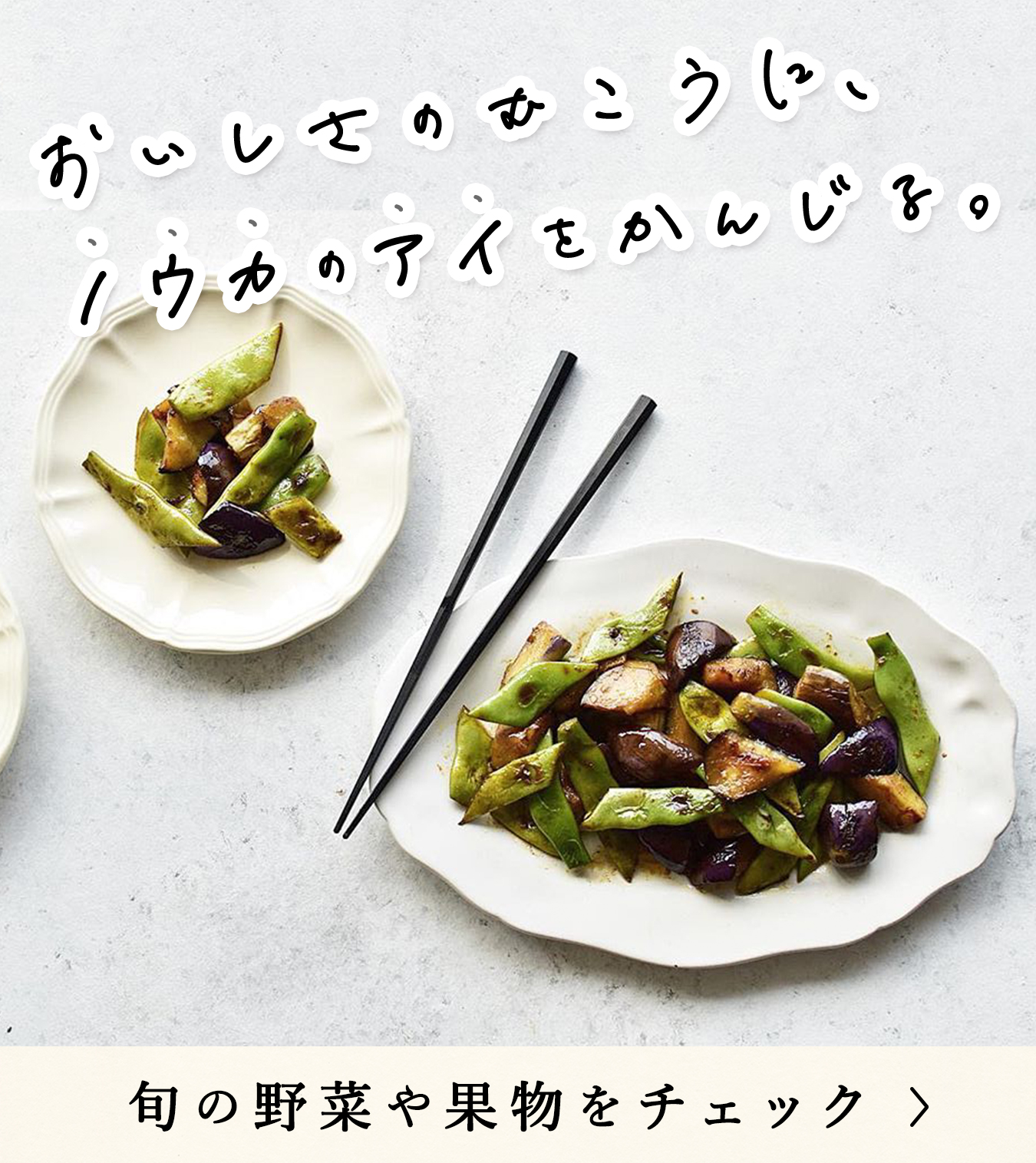日本におけるネギの歴史と勢力図

ネギはユリ科の植物で、原産地は中国西部・中央アジア北部・バイカル地方とされています。
日本には朝鮮半島を経由して8世紀頃に渡ってきました。「日本書紀」にも「ねぎ」と書かれている程、昔から食用として扱われてきています。
ネギの品種は500以上あり、大きく3つの種類に分けられます。3種のうちの2種は白ネギで、残り1種が青ネギとなります。

白ネギの1種は加賀群といいます。白い部分が太いのが特徴で、有名な品種は下仁田ネギです。
夏に成長し、冬は成長が止まって越冬するタイプのネギです。雪が降る地域でも越冬率が高い品種です。

そして、白ネギのもう1つの品種は千住群。1年中流通している「白ネギ」と言われているもののほとんどは、この品種です。
関東で多く栽培されている品種で、夏だけではなく冬にも成長し続けます。成長し続ける間に土寄せをして軟白されるので、長ネギとも呼ばれています。

ネギ種類のうち2種類は白い部分を食べるものですが、3種目は「青ネギ」と呼ばれる種類で、「九条群」といいます。九条ネギや博多万能ネギなどが入ります。
土寄せをせずに育て、低温にも高温に強いので1年中流通しています。
ネギは昔から、関東では白い部分が好まれたために白ネギ(根ネギ)が栽培され、関西では根元から葉先まで柔らかく使い切れる青ネギ(葉ネギ)が栽培されていました。
3群のネギの分布図としては、関東中心に千住群、雪深い地方では加賀郡、そして、西日本を中心に九条群となります。
種類によって変わるネギの保存法

▲白ネギの最適な保存方法
このように、ネギは三種三様ですので、品種によって保存方法が違ってきます。
まず、白ネギは土に戻すかのように保存すると長持ちします。
土に埋めるという方法は昔から行われていますが、新聞紙などに包んで冷暗所に立てかけて保存しても良いでしょう。ネギは上へ伸びようとする性質があるので、横にしておくと曲がってしまいますのでご注意ください。
また、白ネギを切り分けたらラップで包んで野菜室に入れると乾燥してスカスカになりづらくなります。
次に、青ネギは元々根元から葉先まで柔らかく食べらるように育っているので、そのままでの長期間の保存には向きません。
根の部分を水で濡らしたキッチンペーパーで巻いたあと、さらに新聞紙などでくるんで野菜室で保存するという方法がおすすめです。
他にも、細かく刻んでキッチンペーパーに包んで水気を取り、密閉容器に入れて冷凍する方法もおすすめです。
日本各地の「ご当地ネギ料理」
日本全国で昔から親しまれている食材であるネギは、古くから日本各地で独特の方法で食されています。
今回は、そんな日本各地のネギの楽しみ方を集めてみました。
熊本名物「一文字ぐるぐる」

一文字という種類のわけぎをさっと湯がいて、白根の部分を軸に青い葉の部分をぐるぐると巻き付けます。
そこへ酢味噌や辛味噌を添えて頂きます。
細い青ネギも、ひと口大にきっちり巻き付けることで、ザクっという食べごたえのある食感と独特の香りと甘みを楽しむことができます。
千住ネギの根深汁

池波正太郎の小説を読んだ人は恐らく「家で作りたい」と思ったであろうネギ料理。「剣客商売」・「仕掛人・藤枝梅安」といった作品中に根深汁を食べる情景が描かれています。
池波正太郎ファンでない方も、ぜひ試して頂きたい一品です。
小説の中では、鶏皮やごま油でコクを加えたレシピや、ネギを焼いて甘味を引き立たせた作り方が載っています。どれも千住のネギの魅力を引き立たせる料理です。
福島県、大内宿名物「ねぎそば」

福島県伊那市の大内宿の名物料理に、お蕎麦にまるまる1本のネギが添えられている「ねぎそば」があります。
昔は会津地方で婚礼の際に食べていたそうですが、見た目のインパクトがあるため、今では観光客に人気です。
まとめ
ネギはさまざまな種類があり、薬味から主役までさまざまな場面で活躍します。、ネギのお料理を試してみたいと思われたなら幸いです。
この記事を通してネギのお料理を試してみたいと思われたなら幸いです。
お鍋の具材やお蕎麦の薬味だけでない、ネギの食べ方を楽しんでみてくださいね。
「白ネギ2種類」「青ネギ」を紹介しています。生産者のこだわりを感じられる商品ばかりです。ぜひ覗いてみてくださいね!

タイ、バンコクにて8年間、料理教室コーディネーターなどをしながら、世界各地で料理を学ぶ。
日本帰国後は、タイ料理教室を主宰しつつ、日本の美味しい農産物とアジア料理とのコラボレーション・イベントを企画運営するなど、日本のクオリティの高い食材と出会う活動を行う。また、一児の母としての経験も基に、子ども向け食育ワークショップなどの活動にも力を注ぐ。